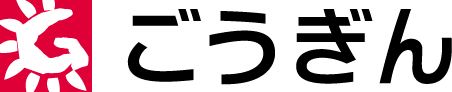
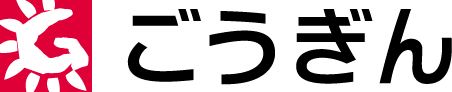

掲載日:2025/09/09

(写真= Adobe Stock)
「高校生になったし、子どもにそろそろお金を自分で管理させたり、キャッシュレス教育をしていきたいけれど、クレジットカードはまだ作れないし、現金だけでは心配」
このような悩みを抱えている保護者にとって、デビットカードは、初めてのキャッシュレス教育のツールとしておすすめです。
この記事では、お子さまにデビットカードを作って持たせる際に、保護者が知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

(写真= Adobe Stock)
高校生以上であれば、デビットカードをお子さま本人の名義で作ることが可能です。
ただし、金融機関によっては、16歳以上でなければ作れない場合や、未成年(18歳未満)が申込む際に、保護者の同意や署名、もしくは保護者の同席が必要となる場合があります。
残念ながら15歳以下の小学生・中学生は、自分名義のデビットカードを発行することはできません。
また、保護者の口座に紐づけた家族カード(デビットカード)を発行することもできません。
ごうぎんの場合も、生計を同一にするご家族への家族カードの発行は、満15歳以上(中学生を除く)からとなっています。
どうしてもデビットカードの代わりとなる決済方法が必要な場合は、プリペイドカードなど、別の手段を検討することになります。
表1:デビットカード作成可能年齢と学年(ごうぎんJCBデビットカードの場合)
| 年齢 | 学年 | ごうぎんJCBデビットカード | 家族カード (デビット) |
|---|---|---|---|
| 14歳 | 中学生 | ✕ | ✕ |
| 15歳 | 中学生 | ✕ | ✕ |
| 15歳 | 高校生/高専生/高校受験浪人生 | 〇 | 〇 |
| 16歳 | 高校生/高専生 | 〇 | 〇 |
| 17歳 | 高校生/高専生 | 〇 | 〇 |
| 18歳 | 高校生/大学生/高専生/専門学生 | 〇 | 〇 |
| 19歳 | 大学生/高専生/専門学生 | 〇 | 〇 |

(写真= Adobe Stock)
満15歳以上(中学生を除く)のお子さまにデビットカードを持たせるメリットは、主に次の7つです。
中でも最大のメリットは、お子さまに対して、お金の管理方法やキャッシュレス決済への意識など、金融教育を実践できる点です。
社会全体がキャッシュレス化しつつある現代では、お子さまが社会に出る前に「お金の使い方」や「キャッシュレス決済」などを実体験で学ばせる意義は非常に大きいと言えるでしょう。
実際に、現金を使う機会が減っている今、お子さまは「お金が減っていく感覚」を掴みにくくなっており、社会人になってクレジットカードを持った際に、「クレジットカードは無限に買い物できる魔法のカード」と誤解して、散財してしまった例もあります。
デビットカードの利用を通じて、お金の管理やキャッシュレス決済を実践させることは、お子さまにとって、学校では教えてもらえない「お金」について大切なことを、実践を通して学ぶ良い機会となるはずです。
それでは、これらのメリットについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
デビットカードは、クレジットカードのように利用から支払いまでタイムラグがなく、支払いと同時に預金口座からお金が引落とされる仕組みになっています。
現金と同じような感覚で使える上、スマートフォンアプリで「何に使ったか(利用履歴)」や「今いくら残っているか(残高)」をリアルタイムで確認できるため、現金よりも管理がしやすいのが特長です。
そのため、自然と「収入と支出を管理する感覚」が養われます。
また、利用のたびにメールで通知が届くなど、支出の把握をサポートする機能も備わっています。
このように、デビットカードの利用を通じて日々の収支を簡単に「見える化」できるため、お子さまはお金の自己管理能力や管理意識を自然と身につけることができます。
スマートフォン決済など、キャッシュレス決済が当たり前となっている時代です。
早い段階からデビットカードを通じて、「現金を使わない支払い(キャッシュレス決済)」に慣れておくことで、将来社会に出たときにも戸惑うことがありません。
また、スマートフォンのアプリ課金やコンサートチケットの購入、携帯電話料金など、一部の加盟店での定期的な支払い手段としても利用可能です。
ただし、デビットカードでは支払いできない場合がある点には注意が必要です。
ごうぎんJCBデビットカードで支払いできない主なものは、以下のとおりです。
デビットカードがあれば、さまざまなショッピングを現金なしで行うことができます。
現金を持ち歩かなくて済むため、現金の盗難リスクが減り、カードを紛失したり、盗難に遭った際も、専用ダイヤルに連絡すればすぐに利用停止ができるので、被害を最小限に抑えることが可能です。
万が一不正利用が発生した場合でも、一定額が補償されるため、「お子さまにカードを持たせることが不安」という保護者の方も、安心してお子さまに持たせることができます。
現金は一度盗まれてしまうと、ほとんど戻ってきませんが、デビットカードなら「利用停止手続きで被害を最小限に抑えられる」「補償によって取り戻せる」点が大きなメリットと言えるでしょう。
デビットカードは支払った瞬間に預金口座からお金が引落とされる仕組みです。
残高が不足している場合は、その場で決済エラーとなるため、預金口座に入っている金額以上を利用することはできません。
そのため、「使いすぎ」を防止することができます。
後払いで限度額まで利用できてしまうクレジットカードとは異なり、「気付いたときには請求額が支払えない」といった最悪の事態を防ぐことができます。
また、支払い遅延(延滞)によってお子さまの信用情報に悪影響が及ぶ心配もありません。
ご家族で同じ金融機関の預金口座を持っていれば、スマートフォンアプリやインターネットバンキングで24時間365日いつでも無料で振込めます。
また、同じ金融機関の預金口座間であれば即時反映という点も嬉しいポイントでしょう。
たとえば、お子さまが修学旅行先などで「急遽お金が足りなくて困っている」というときも数分で送金が完了します。
夜間や休日でも別の金融機関へ振り込むこともできますが、手数料がかかったり着金まで時間がかかったりするため、ご家族で同じ金融機関を利用しておくといざというときに便利です。
国際ブランド(Visa・Mastercard・JCB)付きのデビットカードなら、日本はもちろん世界中の加盟店で利用できます。
海外留学や修学旅行でも現地通貨をたくさん持ち歩く必要がなく、現地ATMで必要な分だけ引出せるので、両替の手間が省けて便利です。
また、デビットカードには海外での利用や旅行に対して保険がついていることもメリットの一つでしょう。
VisaとMastercardは世界中で使える店が多く、JCBは海外利用だけではなく、国内特典が手厚いのが特徴です。
こうした国際ブランドのデビットカードを持たせておけば、お子さまの活動範囲が広がっても安心して見守ることができるでしょう。
デビットカードで支払うと、現金払いでは得られないポイントやキャッシュバックが受取れます。
貯まったポイントは商品券や他社ポイントなどに交換できるので、普段の買い物をしながらお小遣いを増やす感覚で活用可能です。
ポイント還元やキャッシュバックなどを通じて「お得に賢くお金を使う」ことを学ぶことにもつながります。
カードによって還元率などは異なるため、お子さまの利用シーンに合わせた1枚を選ぶと、より効率よくポイントを貯められておすすめです。
お子さまに持たせるデビットカードを選ぶ際は、ご家庭の方針にもよりますが、以下のポイントを重視して選ぶと良いでしょう。
それぞれ選ぶポイントを具体的に見ていきましょう。
まず確認したいポイントが、ご家族が利用する金融機関と同じかどうかです。
同じ金融機関のデビットカードなら、保護者からお子さまへの振込はネットバンキングやアプリを通じて24時間いつでも即時送金が可能。
手数料も無料になることがほとんどです。
定期的なお小遣いの送金や、急な立て替え・送金もすぐに完了します。
さらに、カードを失くしたときの連絡先が共通なので対応がスムーズで、保護者が使い慣れたサービスならお子さまのサポートもしやすいでしょう。
もちろんご家族と別の金融機関でもデビットカードは作れますが、送金の手間や手数料を考えると、ご家族で同じ金融機関にそろえておくメリットは大きいと言えます。
カードを選ぶときは、毎年かかる「年会費」が永年無料かを必ず確認しましょう。
満15歳以上(中学生を除く)〜17歳(未成年)が作れるデビットカードはほとんどが年会費永年無料ですが、なかには「初年度だけ無料で2年目以降は条件付き」など条件を設けている金融機関があります。
デビットカードにも、クレジットカードと同様に Visa・Mastercard・JCB といった国際ブランドがあります。
これら国際ブランドのデビットカードなら、日本でも海外でもほぼどこでも使えるのが強みです。
国際ブランドがないカードは使える店が限られるため、お子さまに持たせるなら国際ブランド付きを選ぶのがおすすめです。
ネット決済にはフィッシング詐欺やカード情報の流出などの危険が伴います。
まだ何も知らないお子さまだからこそ、次のようなセキュリティ機能が充実したデビットカードを選ぶことが大切です。
デビットカードにもクレジットカードと同様に「使った額に応じてポイントや現金が戻る」キャッシュバックの仕組みがあります。
お子さまがよく使う店やサービスで一番ポイント還元が良いカードかどうかを基準に選ぶのもおすすめです。
カードを紛失したり、盗まれたりしても、お金が戻る補償があるかは必ず確認しましょう。
ほとんどの金融機関は「届出日から〇日前まで」「年間〇万円まで」などの条件付きで不正利用を補償しています。
ただしカードを他人に貸したり、暗証番号を教えたり、といった重大な過失があると補償の対象外になることもあるので、契約前に各金融機関の補償の対象となる条件を必ずチェックしましょう。
万が一に備えた補償が手厚いカードを選べば、お子さまに持たせる際の安心感が高まります。

(写真= Adobe Stock)
お子さま名義でデビットカードを作る手順は次の通りで、大人とほとんど同じです。
ただし、18歳未満の未成年者が作る場合は、保護者の同意書や署名、同席などが必要な金融機関があるので注意しましょう。
ごうぎんJCBデビットカードの場合、保護者の同意が必要かどうかの判断基準は次のとおりです。
まずは「どの金融機関で作るか」をご家族で決めましょう。
すでにご家族が預金口座を持っている金融機関があれば、同じ金融機関同士の振込が無料かつ即時反映されるうえ、サポート窓口も共通で便利なのでおすすめです。
もし、新しく選ぶ場合は、「お子さま用のデビットカードを選ぶポイント」を参考に発行する金融機関を選びましょう。
デビットカードを発行するには、お子さま名義の預金口座が必須です。
まだ預金口座がない場合は、まず開設から始めましょう。
満15歳以上(中学生を除く)なら本人だけで手続きできる金融機関がほとんどです。
金融機関によっては保護者の同意書や同席が必要になることがあります。
すでにお子さま名義の預金口座がある場合でも、その預金口座でデビットカードを作れるかは金融機関ごとに異なります。
預金口座の開設、デビットカードの申込み手続きを行います。
デビットカードを申込む前に、まずお子さまの本人確認書類を用意します。
高校生の場合、運転免許証がないことが多いので、マイナンバーカードやパスポート、学生証+住民票など、各金融機関が指定する写真付き書類を確認して準備しましょう。
満15歳(中学生を除く)〜17歳(未成年)の場合は、金融機関によって保護者の同意書や同席が必要になることがあります。
必要書類がそろったら申込みに進みます。
方法は次の3つです。
近年はスマートフォンやパソコンだけで申込みを完結できる金融機関が増えています。
申込みが終わると金融機関で発行処理が行われ、早ければ 1週間〜2 週間ほどでカードが自宅に届きます。
受取り時に本人確認書類の提示やサインを求められる場合があるので、不在時は不在票から再配達を手配しましょう。
カードが届いたら、WEBサービスへの登録を行い、利用通知設定等を行いましょう。
これらをご家族で一緒に設定しておけば、「1日〇円までにする」「使ったらメールが届く」などルールを確認しながら安全に使い始められます。
最後に、お子さまにデビットカードを持たせる際によくある質問をいくつかご紹介します。
満15歳以上(中学生を除く)なら、お子さまの本人名義の預金口座を開設してデビットカードを発行できるため、ご家族が同じ金融機関に預金口座を持っていなくても問題ありません。
お子さま名義のデビットカードは、原則としてご家族と履歴が共有されません。
ただし、金融機関のアプリで家族間の預金口座明細を確認できます。
お子さまの利用履歴を定期的に見たい場合は、次のような家族ルールを決めておくと安心です。
明細を一緒に確認する時間をつくれば、金融教育の良い機会にもなるはずです。
可能です。
ほとんどのデビットカードは、1回・1日・1か月ごとの利用上限をアプリ等で、いつでも変更できます。
たとえば「1日1万円」「1か月5万円」と決めておけば、使いすぎや不正利用があっても被害を最小限に抑えられます。
海外利用をオフにするなど、利用シーンを絞る設定も可能なので、カードが届いたら家族で相談して上限額や制限を決め、必要に応じて見直しましょう。
お子さまにデビットカードを持たせる上で保護者が知っておくべき情報について詳しく解説しました。
お子さまに早いうちからデビットカードを持たせることは、お子さまにとって有意義な体験になるはずです。
ごうぎんJCBデビットカードは、年会費永年無料で、満15歳以上(中学生を除く)であれば、誰でも申込むことが可能です。
ぜひデビットカードの発行をご検討ください。